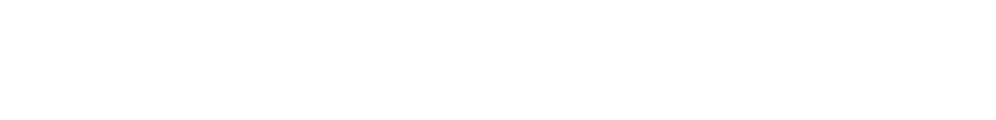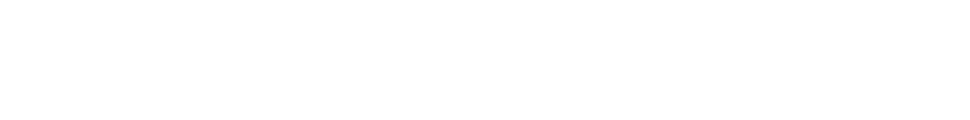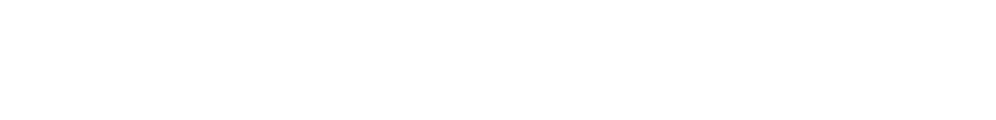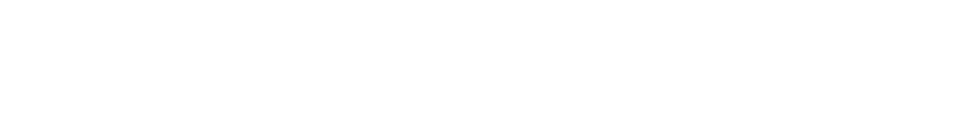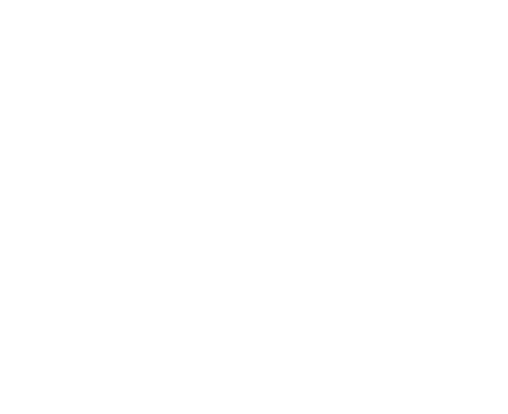Service |
/ 当社のご提供するサービス |
|---|
株式会社とやまかいごは
ヴィレメディカル&ケアグループの一員です。
看護・介護・福祉をご提供しております。

看護小規模多機能型居宅介護
とやまかいごの看護小規模多機能型居宅介護【かんたき】では通い・泊まり・訪問介護・訪問看護などの居宅生活における医療・介護サービスを慣れ親しんだスタッフにより包括的に提供いたします。また通常の介護サービスよりも看護師が多く配置されており医療ニーズの高い利用者様でも対応可能です。またグループ内の医療機関である「とやまクリニック」と連携し医療・介護のシームレスなサービスが提供可能です。利用料金も介護度による月定額制が基本のため安心して利用することができます。
*食事・宿泊した場合の料金など別途かかる料金もあります。
住宅型有料老人ホーム
看護小規模多機能型居宅介護に併設しています。独居や在宅での療養が困難になってきた方が同じ施設内の看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用することで安心した生活を送ることができます。
訪問看護ステーション
とやまかいごの訪問看護ステーションでは経験豊富なスタッフが在宅療養・末期癌等による看取りまでをサポートいたします。また理学療法士・作業療法士による在宅でのリハビリテーションも提供しています。グループである「とやまクリニック」はもちろん、他の医療機関とも連携を取りサポートいたします。
訪問看護についてはこちらもご覧ください
居宅介護支援事業所
ケアプラン(居宅サービス計画)の作成のほか、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請の代行を行います。経験豊富なケアマネージャーが多数在籍し、とやまかいごグループ内のサービスのご利用はもちろん、他の事業者でもご本人様に寄り添った最適なサービスの提供を行えるように心がけております。
児童発達支援事業
放課後等デイサービス
星とたんぽぽでは、落ち着いた環境の中で一人ひとりに合わせた療育を行います。星とたんぽぽでは応用行動分析【ABA】を用いた個別指導を取り入れております。また、保護者様と相談をしながらお子さまの発達段階や、興味に寄り添った療育を準備してすすめさせていただきます。
ABOUT |
/ 株式会社とやまかいごについて |
|---|

平素より、株式会社とやまかいごに格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当社は「いつもそばに」を企業理念としております。これはご利用者様、ご家族様が「私たちが、まるでいつもそばにいる」かのように安心して過ごしていただけることを目指している言葉です。当社には様々な種類の仕事が存在しますが、どんな仕事をする場合でもこの理念をいつでも忘れずに、私たちの指針として深く心に刻み行動をいたします。
看護小規模多機能型居宅介護は、医療処置が必要な方が看護師のケアを受けることができ、住み慣れた自宅にいながら「通い」「訪問」「泊り」と多機能性を活用した介護を受けられることが特徴です。当社は時代のニーズに合った施設として確信しており、ここに経営資源を集中してまいります。2018年にぱるす(清水区谷田)を皮切りに、2020年にすぴか(駿河区東新田)2022年にりいふ(葵区瀬名川)を開業いたしました。2023年3月にびおら(藤枝市高柳)、2024年度も焼津市、富士市に2施設を開業予定です。
医療法人社団ヴィレとやまクリニックを母体に持ち、トータルケアを目指すべくケアマネ事務所、訪問看護ステーションも併設しております。
また、「インクルージブ」(社会的包摂)の観点から、2022年には児童発達支援事業所・放課後等デイサービス「星とたんぽぽ」(葵区新富町)を開業いたしました。
このように多様な方面に事業を展開している当社ですが、利用者様・ご家族の安心を最優先とすることは企業理念のとおりであり、それを実現するには、長期安定的な経営とともに、サービスの直接提供者であるスタッフの量・質の確保が根本であることは間違いありません。今まで以上に良質な採用・育成・教育に取り組んでいきたいと思います。
「いつもそばに」株式会社とやまかいごに今後とも末永くご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
本社所在地
〒421-0112
静岡市駿河区東新田3丁目32-9
電話:054-257-9810
FAX:054-201-9750
事業所
・ぱるす看護小規模多機能型居宅介護
・ぱるす訪問看護ステーション
・すぴか看護小規模多機能型居宅介護
・すぴか住宅型有料老人ホーム
・すぴか訪問看護ステーション
・りいふ看護小規模多機能型居宅介護
・りいふ住宅型有料老人ホーム
・びおら看護小規模多機能型居宅介護
・びおら訪問看護ステーション
・びおら住宅型有料老人ホーム
・介護プラン虹
・星とたんぽぽ
有資格者人数
|
看護師
|
18名 |
|---|---|
|
理学療法士
|
4名 |
|
作業療法士
|
1名 |
|
介護支援専門員
(ケアマネジャー) |
13名 |
|
介護福祉士
|
20名 |
| 保育士 | 4名 |
とやまかいご看取りに関する指針(令和5年3月改訂版)
看取り介護の考え方
看取り介護とは、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことが出来るように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象者の尊厳に充分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行うことである。
看取り介護の視点
終末期の過程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられる。施設での看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えられることであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得る。
①施設における医療体制の理解・常勤医師の配置がないこと。
・訪問看護ステーション又はかかりつけ医師と連携し、必要時は24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応すること。
・夜間は看護師が不在で、緊急時へ施設責任者への連絡により駆けつける体制であること
・病状の変化等に伴う緊急時の対応については施設責任者が訪問看護ステーションおよびかかりつけ医師と連絡をとり判断すること。
・夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき上記責任者と連絡をとり、緊急対応を行うこと。
・家族との24時間の連絡体制を確保していること
②看取りの介護に対する本人または家族の同意を得ること。
看取り介護の具体的支援内容
1)基本的な指針
①終末期の経過(時期、プロセスごと)の考え方を、職員全体で共有化する。定期的におこなわれる毎日の申し送りの際、「ターミナルケア」として状態把握を詳細に行っていくことを確認する。(看取りに入った時点で、看取りのためのノート又はサービス提供票を作成する)
②看取り態勢となった場合の医療処置の基準の確認(医師、家族との確認。これ以上の手当てはしない。)
・点滴(水分のみ。日中のみ)
・酸素療法は(自発呼吸をサポートする。)
・口腔ケア 口呼吸になると乾くので保湿剤を塗る
・浣腸 必要に応じて
・解熱剤
2)利用者に対する具体的支援
①ボデイケア
・バイタルサインの確認・環境の整備を行う・安寧、安楽への配慮
・清潔への配慮
・栄養と水分補給を適切に行う・排泄ケアを適切に行う・発熱、疼痛への配慮
②メンタルケア
・身体的苦痛の緩和・コミュニケションを重視する・プライバシーへの配慮を行う
・すべてを受容してニーズに沿う態度で接する
3)家族に対する支援
・話しやすい環境をつくる
・家族関係への支援にも配慮する
・希望や心配事に真摯に対応する・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する
・死後の援助を行う
看取り介護の具体的方法
1)看取り介護の開始時期
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断して回復の見込みが無いと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、医師より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、(看取り介護に関する計画を作成し)終末期を在宅または施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施されるものである。
2)医師よりの説明
①医師が1)に示した状態で、看取り介護の必要性があると判断した場合、看護職員またはソーシャルワーカーを通じ、当該利用者の家族に連絡をとり、日時を定めて、医師より利用者または家族へ説明を行う。施設責任者の立会いを要請し、施設でできる看取りの体制を示す。
②この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が在宅または当施設で看取り介護を受けるか、医療機関に入院するか選択することができる。医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に向けた支援を行う。
3)看取り介護の実施
①家族が施設内で看取り介護を行うことを希望した場合は、介護支援専門員と連携をとり、医師、看護職員、介護職員、食事スタッフ等と共同して看取り介護の計画を作成する。なおこの計画は、医師からの利用者又は家族への説明に際し、事前に作成しておき、その際に同意を得ることも考えられる。
②看取り介護の実施に関しては、家族が泊まりを希望する場合は便宜を図る。
③看取り介護を行う際は、施設責任者が週に一度以上定期的に利用者または家族への説明を行い同意を得る。
④全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死をむかえることができるように、利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的支援に努める。
夜間緊急時の連絡と対応について
当施設の夜間緊急時の連絡・対応マニュアルによって適切な連絡を行うこと。
かかりつけ医、訪問看護ステーション、協力医療機関、とやまクリニックとの連携体制
当該利用者のかかりつけ医及び訪問看護ステーション、その他強力医療機関、とやまクリニックとの連携により、365日、24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制をとる。
責任者
夜間緊急対応および看取り介護については、施設長を責任者とする。
利用者死亡後の対応
あらかじめ確認しておいたとおりに、医師への伝達方法と死亡確認書の作成が行われる。
したがって、事前に家族および関係職員への連絡方法を確認しておく。
死後の遺体処置がおこなわれ、本人、家族の意向に沿った遺体の引渡しがおこなわれる。
同時に葬儀方法、場所、職員のかかわり方など家族の意向に対する対応を行う。
附則 令和5年3月14日より、この指針を実施する。